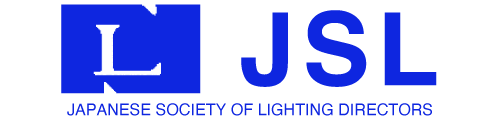日本映画テレビ照明協会 沿革
| 昭和34年 (1959) | 「日本映画照明新人協会」として発足。 当時の各撮影所の照明助手を以て組織し 初代会長は大映所属の中島康夫で事務局は藤野。会計は東宝の蝶谷が担当。 |
| 昭和40年 (1965) | 「日本映画照明技術者協会」と改称され、引き続き大映の中島が担当。
一期2年とし技師も参加。 名実ともに日本の照明技術者の組織となる。 |
| 昭和43年 (1968) | 日本映画照明技術者協会編纂による「映画照明」判199頁を刊行。 今では幻の黒表紙と呼ばれ、再刊行を望む声が多い照明技術専門誌である。 |
| 昭和44年 (1969) | 「照明技術賞」が設定され、技術の向上にその役割を果たしている。 助手を含めての表彰は当協会の特色でもある。 |
| 昭和45年 (1970) | この年に行われた技術賞受賞パーティーが現在の「照明まつり」に発展したものであり。とぎれることなく、現在まで開かれている。 席上各技術賞及び協会賞の発表、授賞が行われ。関連団体・維持会員社・正会員及顧問並びに名誉会員各位の祝福を受け、 技術の向上の証となっている。 |
| 昭和47年 (1972) | 機関紙「映画照明」第1号を発行 (年2回) 20号より「映像照明」と改題。 |
| 昭和48年 (1973) | 「スポット」創刊号を発行。タブロイド版2ページ (年6回) 会員への案内・連絡誌として発行。 |
| 昭和59年 (1984) | 職能の連合体である監督、撮影、美術、照明の4団体で発足し、現在では録音、編集、スクリプター、プロデューサーの4団体も参画し8団体となり、 日本映像職能連合の一員として映像文化の発展に微力ながら尽力している。 |
| 平成3年 (1991) | 文化庁の要請による、国内芸術インターンシップ研修員に当協会からは翌平成4年より研修員2名を選出。 平成7年国内芸術研修員制度には4名を送っている。 |
| 平成7年 (1995) | 会員共済制度の充実を目的に全労済団体生命共済に加入。 冠婚葬祭・出産・病気見舞い・会員死亡時弔慰金30万などの運営がなされている。 |
| 平成9年 (1997) | 「協同組合 日本映画・テレビ照明協会」の設立許可を受ける。 |
| 平成13年 (2001) | 定期総会において協会の名称「日本映画照明協会」を「日本映画テレビ照明協会」に改称する議案が承認され 「協同組合 日本映画・テレビ照明協会」と併記、運用されることとなる。 |
| 平成15年 (2003) | 現在、正会員は、本部会員、各支部会員とグループ会員で構成され、
名誉会員34名、顧問1名を含む会員575名が協会員である。 また当協会には関連企業各社を主とした維持会員制度があり、その数65社に及び 、協会の発展と相互技術の進歩に大きく貢献している。 他に、照明を理解し賛同する他業種の方々も賛助会員として参画。 現在会長以下29名の役員によって協会活動の日常が運営され。年一回の総会に依って決定が行われる。 尚、今までに名誉会員の故岡本 健一氏、元会長の故伊藤 幸夫氏、前会長故下村 一夫氏 が勲四等瑞宝章の叙勲を受けている。 |
| 平成31年 (2019) | 日本映画テレビ照明協会設立60周年。 照明まつり」 第50回が4月24日調布市グリーンホール 小ホールにて開催される。 機材展示会社18社含む授賞式・パーティー参加者は総勢191名になり同時開催の機材展(展示ブース19区画)には90名の参加。 各方面の関連団体及び俳優、女優様方よりお祝いの メッセージを頂戴し、会場前を豪華に飾って頂く。 |
歴代会長
| 就任年 | 氏名 | 所属 |
| 昭和34年 (1959) | 中島 康夫 | 大映 |
| 昭和41年 (1966) | 高松 宣明 | 松竹 |
| 昭和42年 (1967) | 蓮本 正俊 | 松竹 |
| 昭和43年 (1968) | 森 弘充 | 東宝 |
| 昭和44年 (1969) | 藤林 甲 | 日活 |
| 昭和45年 (1970) | 伊藤幸夫 | 大映 |
| 昭和51年 (1976) | 藤林 甲 | 日活 |
| 昭和52年 (1977) | 山口 虎男 | 東宝 |
| 昭和53年 (1978) | 石井 長四郎 | 東宝 |
| 昭和55年 (1980) | 平田 光治 | フリー |
| 昭和61年 (1986) | 下村 一夫 | フリー |
| 平成12年 (2000) | 熊谷 秀夫 | フリー |
| 平成20年 (2008) | 佐野 武治 | フリー |
| 平成23年 (2011) | 望月 英樹 | フリー |